
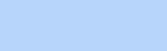

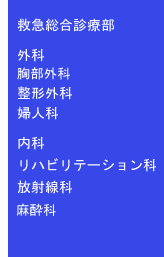













| 『腹腔鏡下手術を受けられる方へ』 | ||||||||||||||||||||||
| 1. 腹腔鏡を用いた手術(検査)とは 腹腔鏡とは、お腹の中を観察することを目的とした内視鏡のことです。通常、臍のあたりの小さな切開創(10mm程度)から腹腔内(体内)に望遠鏡のような内視鏡を挿入し、その切開創から炭酸ガスを注入して空間を作り手術視野を確保します。腹腔内から得られた様々な情報をモニターテレビに写し出し、このテレビ画像の下に下腹に追加した3〜4カ所の小切開創(通常5mm)から手術器具(鉗子、電気メス、超音波メスなど)を操作して手術を行います。 その結果、今までの開腹して行う手術に比べてお腹の傷が小さくてすみ、手術後の痛みは軽く、入院期間も短縮されます。 |
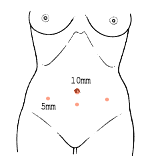 |
|||||||||||||||||||||
| 2. この手術の適応となる産婦人科の疾患とは 不妊症 子宮外妊娠 卵巣嚢腫 子宮内膜症 子宮筋腫 その他 3. この手術の適応とならない場合とは 全身麻酔ができない方 腹腔鏡が適切でない方 著しい肥満の方 腹腔鏡のメリットを生かせない症例 何度も腹部の手術を受けておられる方 その他、医師が適応でないと判断した場合など |
||||||||||||||||||||||
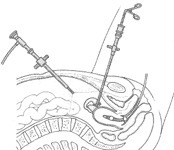 |
||||||||||||||||||||||
| 4. 手術に必要な主な検査内容 普通の開腹手術と同じ内容の検査です。 血液検査、心電図検査、肺機能検査、超音波断層検査、MRI検査など |
||||||||||||||||||||||
| 正常所見(両側の卵巣、卵管の様子) | ||||||||||||||||||||||
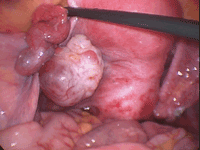 |
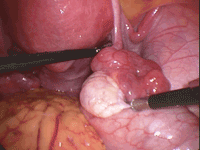 |
|||||||||||||||||||||
| 卵管切開し、胎嚢を取り出す。 | ||||||||||||||||||||||
| 子宮外妊娠手術(卵管温存例) | ||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
| 右卵管妊娠(膨大部)。妊娠6週程度。 | ||||||||||||||||||||||
| 卵巣腫瘍(Total Laparoscopic Cystectomy) | ||||||||||||||||||||||
 |
核出後(縫合する前) | |||||||||||||||||||||
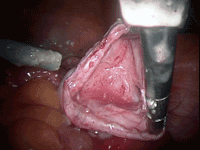 |
||||||||||||||||||||||
| 両側卵巣腫瘍(皮様嚢腫) | ||||||||||||||||||||||
| 【合併症について】 1. 手術手技によるもの 腹腔鏡下手術による合併症の頻度は高くはありませんが、まれに後日全身麻酔下に緊急開腹を要する場合もあります。合併症としては、消化管損傷、尿路損傷、腹膜炎(多くは癒着剥離時の損傷、電気メスによる火傷)、出血、感染、腹壁ヘルニア、腸閉塞などが挙げられます。 2. 麻酔によるもの 腹腔鏡下手術では、腹腔内に二酸化炭素を送り込んで、ドーム状に腹壁を持ち上げて作った空間で手術をします。それに伴うよくある合併症に、腹壁や横隔膜が引き延ばされて起こるみぞおち、脇腹、背中から肩先にかけても痛みがあります。稀なものに、皮下気腫、気胸、ガス塞栓、深部静脈血栓症に伴う肺塞栓などがあります。特に、後の2つには、きわめて稀ですが死亡例の報告があります。 3. 手術体位によるもの 婦人科の腹腔鏡下手術では、ベッドの傾斜を頭側に10度位下げて行うので、ベッドから転落しないように手足や肩をベッドに止めます。その際、神経を圧迫しないよう注意しますが、稀に、手足のしびれ感などがでる場合がありますが、通常は数日以内で回復します。特に、手足の関節の病気、神経痛、脊椎の病気などのある方には一層の注意が必要となりますので、事前にお知らせ下さい。 【麻酔について】 麻酔は、麻酔科の専門医師が担当し、麻酔方法は全身麻酔と硬膜外麻酔を併用し安全第一に全身管理いたします。もし質問などありましたら、麻酔科医師からの説明の時にお尋ね下さい。 一般的には内視鏡手術は低侵襲といわれております。ほとんどの患者さんにとっては回復が早く、社会復帰が早い、美容上も優れているなどの点で有益と考えられていますが、再手術を要するような合併症の頻度は、従来の開腹手術よりむしろ高いのが現状です。 腹腔鏡下手術に替わる治療として、従来法である開腹手術があります。この開腹手術でも合併症は存在します。すなわちイレウス、尿路損傷、腹膜炎、出血などのほか術後の痛みが強い、術後の回復に時間を要する、腸管の癒着が起こりやすいなどの課題点があります ※注 意 腹腔鏡による手術は、手術による侵襲性を少なくして、かつ安全に行おうとするものです。もしも、腹腔鏡による手術が無理であると判断した場合、手術操作による合併症が生じた場合、などでは速やかに開腹手術に切り替えて対応します |
||||||||||||||||||||||
| 参考:子宮鏡(ポリープ切除) | ||||||||||||||||||||||
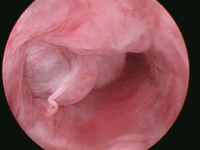 |
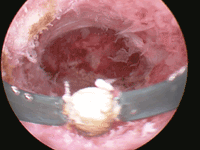 |
|||||||||||||||||||||